特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?

▼特定技能「工業製品製造業」とは
-概要
特定技能制度は、2019年4月に設けられた在留資格制度です。人手不足が深刻な分野において、即戦力となる外国人材の受け入れを目的としています。
そのなかでも特定技能「工業製品製造業」は、機械金属加工や紙器・段ボール箱・コンクリートの製造などの分野で就労することを前提にした外国人材が取得する在留資格です。
従来の3分野が統合して特定技能「工業製品製造業」に変更-概要
特定技能の製造分野は、従来は「産業機械製造」「電気・電子情報関連産業」「素形材産業」の3分野が設けられていました。
しかし、「産業機械製造業」における特定技能人材が受け入れ見込み数を超える状況となってしまい、令和4年4月1日以降は新規受け入れが停止となりました。
ただ、製造業における人材不足はまだまだ続くことが想定されたため、制度の見直しを図り、3分野を統合して「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」となりました。
その後、名称を変更し、「工業製品製造業」となって業種や業務区分も変更がおこなわれました。
受入れ可能な企業の産業分類
特定技能「工業製品製造業」の人材を受け入れられる企業は、以下の産業分類に属している企業です。
| ◾️1号・2号どちらも受け入れ可能 ・鋳型製造業(中子を含む) ・鉄素形材製造業 ・非鉄金属素形材製造業 ・機械刃物製造業 ・作業工具製造業 ・配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) ・金属素形材製品製造業 ・溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) ・電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) ・金属熱処理業 ・その他金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る) ・ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 ・はん用機械器具製造業(ただし、消火器具・消火装置製造業を除く) ・生産用機械器具製造業 ・業務用機械器具製造業(ただし、医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く) ・電子部品・デバイス・電子回路製造業 ・電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業を除く。) ・情報通信機械器具製造業 ・工業用模型製造業 |
| ◾️1号のみ受け入れ可能 ・繊維工業 ・パルプ製造業 ・洋紙製造業 ・板紙製造業 ・機械すき和紙製造業 ・塗工紙製造業(印刷用紙を除く) ・段ボール製造業 ・紙製品製造業 ・紙製容器製造業 ・その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 ・印刷・同関連業 ・プラスチック製品製造業 ・コンクリート製品製造業 ・食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 ・陶磁器製置物製造業 ・高炉による製鉄業 ・高炉によらない製鉄業 ・製鋼・製鋼圧延業 ・熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く) ・冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く) ・鋼管製造業 ・鉄素形材製造業 ・鉄鋼シャースリット業 ・他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。) ・鉄骨製造業 ・金属製サッシ・ドア製造業 ・製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。) ・金属製品塗装業 ・他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。) ・他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。) ・こん包業 |
参照:製造業における特定技能外国人材の受入れについて(工業製品製造業分野) 2024年11月 経済産業省
上記の産業分類に属しているかつ、特定技能人材が従事する事業所において、直近1年間で製造品出荷額などが発生している必要があります。
特定技能「工業製品製造業」受入れ見込み人数
特定技能「工業製品製造業」では、令和6年4月から5年間の受入れ見込み数が173,300人となっており、特定技能16分野の中でも最大の規模が見込まれています。
令和5年度末までの受入れ見込み数が49,750人だったことを考えると、大幅な状況の変化が見込まれることがわかります。
専門的な知識や技能を備えている外国人材を受け入れられる制度を活用できることは、業界の人手不足を解決するきっかけとなるでしょう。
▼特定技能「工業製品製造業」で従事できる業務
工業製品製造業分野で特定技能人材が従事できる業務は、以下の10区分です。
| 区分 | 概要 |
| 機械金属加工区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事 |
| 電気電子機器組立て区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事 |
| 金属表面処理区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、表面処理等の作業に従事 |
| 紙器・段ボール箱製造区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事 |
| コンクリート製品製造区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事 |
| RPF製造区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事 |
| 陶磁器製品製造区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事 |
| 印刷・製本区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事 |
| 紡織製品製造区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事 |
| 縫製区分 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、縫製工程の作業に従事 |
参照:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
▼工業製品製造業界の現状
製造業全体の就業者数は減少傾向にあり、慢性的な人手不足に悩まされています。
過去20年間の推移で見ると、2002年は1,202万人でしたが、2024年は1,046万人と約150万人に達する規模で減少しています。
加えて生産労働人口自体も減少を続けるなか、全産業に占める製造業への就業者数の割合は低下傾向にあるため、依然として人材確保は大きな課題となっています。
技能実習「工業製品製造業」から移行する人材が多い
工業製品製造業界では、すでに多くの外国人材が就労しており、外国人材に助けられている傾向も強いです。厚生労働省によると国内産業でもっとも外国人労働者を受け入れているのは製造業とされています。
また、特定技能「工業製品製造業」は技能実習から移行する人材も多いです。
技能実習とは、日本で業務をおこなうことで知識や技術を身に着け、母国に持ち帰って経済発展に役立てていく国際貢献の推進が目的の制度です。
2016年より技能実習生の受け入れはおこなわれ、大変優秀な外国人労働者が訪日し、数多くの事業所で活動をおこなっています。
ただ、技能実習制度は、通年して5年間の期間が定められており、その後は母国に帰国することが義務付けられています。(1号:1年間、2号:2年間、3号:2年間)
そのため特定技能は、技能実習の期限が切れてしまう外国人材に継続して就労してもらうための、受け入れ先のような制度にもなっています。特定技能1号に移行することで、通算で5年間就労することが可能です。
技能実習で知識や技術が身についた外国人材を受け入れられるため、即戦力として活躍が期待できます。
▼特定技能「工業製品製造業」を取得するには
特定技能「工業製品製造業」には、1号と2号の2種類があります。
1号は基礎的な知識と技術を必要とする業務に従事する人材向けの資格で、2号は熟練した知識や技術を必要とする業務に従事する人材向けの資格です。
1号と2号はそれぞれ取得の要件が異なります。
1号は試験の合格もしくは技能実習からの移行
1号の取得方法は、以下の2パターンあります。
- 試験に合格して取得
- 技能実習から移行して取得
1つ目の「試験に合格して取得」は、評価試験・日本語試験に合格する必要があります。
評価試験は一定の専門性・技能を用いて即戦力として就労するために、必要な知識や経験を備えていることを確認するための試験です。試験の形式は、テストセンターにてコンピュータを使用して実施する「CBT方式」で、学科試験30問・実技試験10問の計40問が出題されます。学科試験が65%以上、実技試験が60%以上の正答率で合格です。
日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力検定(N4以上)」の合格が必要です。日本語能力試験はN1からN5まであり、N4は「基本的な日本語を理解することができるレベル」です。
2つ目の「技能実習から移行」は、技能実習2号を良好に修了した場合、1号への移行が認められます。技能実習2号の業務内容と、1号の業務との関連性があると認められる場合には、評価試験と日本語試験は免除されます。また、移行後の業務と技能実習の職種が異なる場合であっても、良好に修了していれば日本語試験は免除されます。
2号は試験の合格と実務経験が必須
2号は、1号の修了者のステップアップとして取得する場合が一般的です。
ただし、1号で通算5年経過すれば自動的に移行となる訳ではなく、試験の合格と実務経験が必要となります。
試験は、以下のいずれかに合格することが条件です。
- 「2号評価試験」および「ビジネス・キャリア検定3級」
- 「技能検定1級」
また、実務経験は、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要です。そのため、自社で働いている外国人材に2号の取得を検討している場合は、在留期限を見越して実務経験を積ませることが重要となります。
▼試験について
評価試験を受験するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 試験受験日において、満17歳以上である(インドネシアでの試験では満18歳以上)
- 日本国籍を有しない
- 在留資格を有している
試験の形式は、テストセンターにてコンピュータを使用して実施する「CBT方式」です。日本国内もしくは、インドやインドネシア、フィリピンなどの海外で実施されます。
試験の内容は、学科試験30問・実技試験10問の計40問が出題されます。学科試験が65%以上、実技試験が60%以上の正答率で合格です。
試験の情報については、経済産業省が運営している「製造分野特定技能評価試験」のWebページにて掲載されています。受験日や試験の申請方法などについて詳しく知りたい方は、Webページを確認してください。
▼1号特定技能外国人受け入れまでの流れ
1号特定技能人材を受け入れる際は、以下の流れでおこないます。
- 製造業特定技能外国人受け入れ協議・連絡会への入会
- 受け入れる外国人材の探索・選考
- 特定技能外国人支援計画の策定
- 受け入れる外国人材と雇用契約の締結
- 出入国在留管理局への在留資格関連の申請
- 特定技能外国人の就労開始
順番ごとに流れを解説していきます。
①JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)への入会
まずは、自社が対象業種に該当するか・特定技能人材が従事できる業務をおこなっているか、確認しましょう。
問題なければ、JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)への加入手続きに向けて書類を準備します。
JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)とは、特定技能人材の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体です。工業製品製造業分野で特定技能人材を雇用している事業所や今後雇用しようとしている事業所は、JAIMへの入会が必須となります。
これから工業製品製造業分野の人材を雇用する企業は、JAIMのホームページから必要書類をダウンロードし、入会の手続きをおこないましょう。
必要書類は以下の通りです。
- 行動規範に係る誓約書
- 反社会的勢力でないことの表明・確約に係る誓約書
- 生産性向上及び国内人材確保のための取組に係る誓約書
- 従業員数証明書
- 製造品証明書類テンプレート等
不明点がある場合は、JAIMの相談窓口に相談しましょう。
| 一般社団法人工業製品製造技能人材機構 相談窓口電話番号:03-6838-0077 メールアドレス:seizou_tokuteiginou_soudanmadoguchi@jaim-skill.or.jp 公式ホームページ:https://www.jaim-skill.or.jp/ |
②受け入れる外国人材の探索・選考
JAIMへの入会手続きが完了したら、受け入れる外国人材の探索・選考をおこないます。
外国人材の探索には以下の方法があります。
- 人材紹介業者を利用
- 自社の外国人材から知り合いを紹介してもらう
- 求人サイトでの求人掲載
- 自社のホームページやSNSで求人掲載
初めて採用をおこなう企業は、人材紹介業者を活用するのがおすすめです。人材の募集から面接の設定などを着実に実施してくれるので、スムーズに採用活動を進めることができます。
候補者が集まったら、書類審査と面接にて選考を実施し、募集要項に合う人材に絞り込んでいきます。
③特定技能外国人支援計画の策定
1号の人材を受け入れる場合、「義務的支援」として、職業生活上・日常生活上の支援をおこなう必要があります。そのため受け入れる外国人材が決まった際には、「特定技能外国人支援計画」として支援の内容をまとめ、ビザ取得申請の際に提出しなければなりません。
支援計画で策定することは以下の10項目です。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの内容を定めて、支援計画を策定しましょう。
④受け入れる外国人材と雇用契約の締結
受け入れる外国人材が決まれば、雇用契約の締結をおこないます。この時発行する雇用契約書は、国籍に合わせた言語で作成しましょう。
外国人材は一定の日本語は理解していると思いますが、まだまだ日本語の理解がスムーズでない可能性もあります。
その場合、日本語のものを発行すると、あまり内容を理解していないまま締結してしまうおそれがあります。後々のトラブル防止のために、国籍に合わせた言語で書類を作成しましょう。
⑤出入国在留管理局への在留資格関連の申請
雇用契約締結後は、出入国在留管理局へ在留資格関連の申請をおこないます。申請は外国人材が来日してくるか、すでに日本に在留しているかによって内容が変わります。
- 海外から来日する外国人の場合:在留資格認定証明書交付申請
- 日本国内に在留している外国人の場合:在留資格変更許可申請
正しく申請しなければ不法就労となってしまうおそれもあるので注意してください。
⑥特定技能外国人の就労開始
手続きが完了すれば、特定技能外国人の就労開始となります。雇用開始後は、策定した支援内容を必ず実施しましょう。
外国人材受け入れに必要な手続きや支援計画の策定、雇用後の支援を自社でおこなうのが大変な場合は、「登録支援機関」に委託するのも一つの手です。
登録支援機関は、外国人材の雇用に必要な手続きや支援業務を代行する専門機関です。専門的な知識と対応が求められるため、予想以上に負担となることもありますが、登録支援機関へ委託することで外国人材への支援を代行しておこなってくれます。
▼特定技能「工業製品製造業」人材を採用するには
採用のルートは国により異なり、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会にて詳細を確認することをおすすめします。
例えばカンボジア人の場合は現地の斡旋事業者と国内の人材紹介会社を経由しての採用となり、インドネシアやネパールの場合は現地の送り出し法人から斡旋してもらう形になります。フィリピンは少々複雑で、駐日フィリピン大使館海外労働事務所(POLO)が許可を出した後に、フィリピン海外雇用庁(POEA)に認定を受けた現地の斡旋業者が人材を集め、送り出しを行う仕組みです。
【PR】特定技能人材の中途採用はスキルド・ワーカー

2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。
特定技能で外国人材を採用する企業が着実に増える中、特定技能人材側の転職希望者も増えてきました。
そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。
日本人がごく普通に転職するように、技能人材に転職希望者が出てくるのは自然な流れと言えます。
特定技能人材の転職希望者の多くは仕事に対するモチベーションは高いものの、職場環境とマッチしていないがゆえに活躍し切れていないケースがほとんどなのが現状です。
スキルド・ワーカーは、丁寧なヒヤリングと面談によるマッチングを最も重視したサービス。
特定技能人材の中途採用にも力を入れています。
こんなお悩みのあるご担当者様におすすめ!
・日本国内だと業界的に人材不足が著しい
・募集をかけても経験者の応募がなかなか来ない。
・採用してもモチベーション維持や育成に手間がかけられない
スキルド・ワーカーは特定技能人材の採用マッチングから住居/ビサの手続きなどの受け入れ準備、採用までフルサポートいたします。
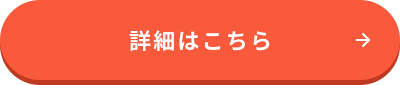
特定技能人材の採用をお考えの皆様へ
今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。
・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
・どのような仕事を任せられるのか?
・どの国の人材が良いのか?
・雇用するにあたり何から始めればよいのか?
…など、様々不安や疑問があるかと思います。
外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。
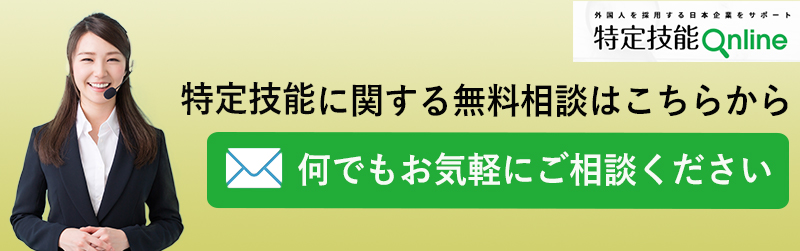


この記事が気に入ったら
いいねをお願いします!
関連記事リンク
-
 特定技能1号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能における在留外国人数は336,196人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能1号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能における在留外国人数は336,196人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 特定技能2号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能2号における在留外国人数は3,073人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能2号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能2号における在留外国人数は3,073人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。
【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。 -
 特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年6月末での特定技能1号における在留外国人数は251,747人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年6月末での特定技能1号における在留外国人数は251,747人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
セミナー情報
-
 【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。
【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。 -
 造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。
造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。 -
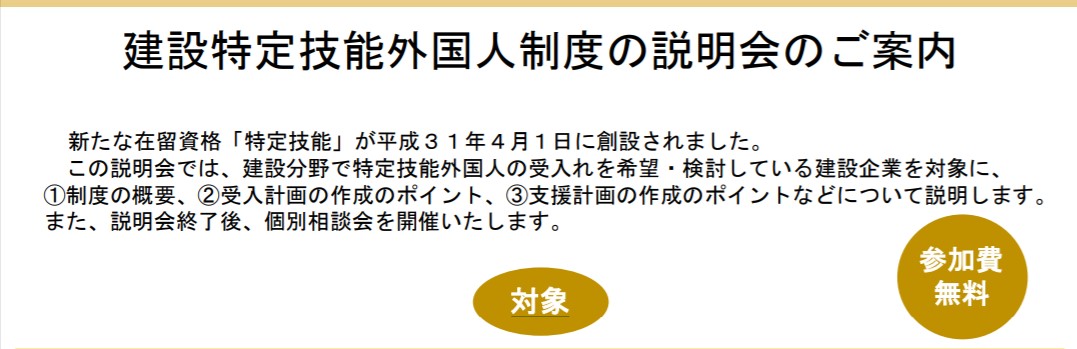 【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。
【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。

-

2025/10/06
特定技能1号 在留外国人数【2025年6月末時点】
-

2025/10/06
特定技能2号 在留外国人数【2025年6月末時点】
-

2025/07/27
特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?
-

2025/03/28
特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】
-

2024/11/15
【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。
-

2024/10/04
特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】
-
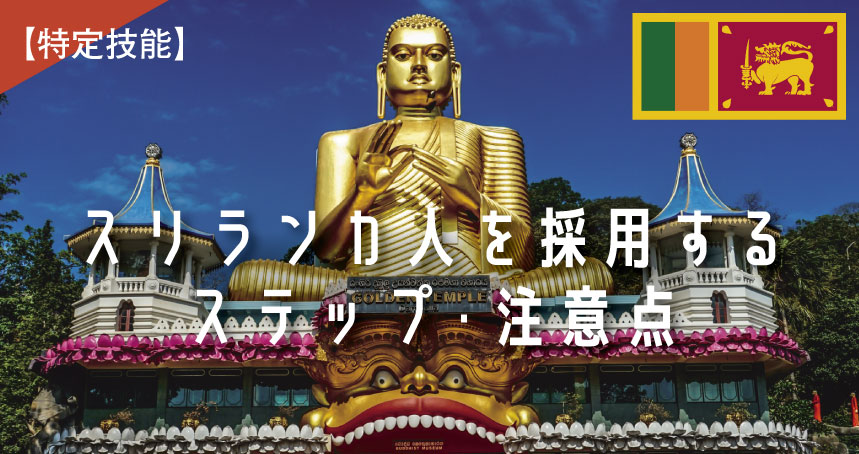
2024/07/31
【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。
-

2024/07/31
【特定技能】ネパール人を採用するステップ・注意点を解説。



