特定技能で人材採用するには|採用する際にかかる費用・期間・準備するべき資料・手続き・おすすめの採用手法を解説

2019年に「特定技能」という在留資格が新設されました。この在留資格による、日本の人手不足の改善が期待されています。
従来の就労可能な在留資格とはどのような違いがあるのか?
どのような採用手順・採用手続きを踏めばよいのか?
このような疑問や悩みを抱える企業や採用担当者の方が増えています。
この記事では、特定技能の在留資格に関する基礎知識や特定技能で人材採用するために必要な準備、手続き、期間などをまとめました。
【おすすめ記事】
特定技能の在留資格で採用できる14種
2019年4月に新しく新設された在留資格「特定技能」。入管法の改正によって導入されたこの資格は特定技能ビザとも呼ばれており、就労ビザに含まれます。特定技能の在留資格によって採用できる業種は、以下の14種類となっています。
| 建設業 | 造船・舶用工業 |
| 自動車整備業 | 航空業 |
| 宿泊業 | 介護 |
| ビルクリーニング | 農業 |
| 漁業 | 飲食料品製造業 |
| 外食業 | 素形材産業 |
| 産業機械製造業 | 電気電子情報産業 |
※素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野が製造業に統合されたため、14分野から12分野(14業種)に変更されました。
特定技能の知識を蓄える上で把握しておきたいのはその種類です。特定技能の在留資格には1号と2号があり、主な特徴や違いは大まかに以下のようになっています。
詳しい特定技能1号と2号の違いについてはこちら。
【特定技能1号】
| 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
【特定技能2号】
| 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
特定技能1号とは即戦力となる人材を受け入れるための受け皿であり、通算5年間は上記の12分野14業種において就労が認められています。
一方の特定技能2号は原則として特定技能の1号修了者が次のステップとして進む資格となっており、1号の資格取得者よりも熟練した能力を持つ人材を確保するために設けられた在留資格です。
また特定技能1号と2号では受入れ可となる業種の数が異なります。特定技能1号は上記全14の業種で就労可能となっていますが、特定技能2号は建設および造船・舶用工業の2種のみが対象です。(改正予定)
介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となることが令和5年6月に閣議決定されました。
開始時期は未定で、開始時期が決まり次第 出入国在留管理庁のHPで発表されます。
特定技能制度で採用できる4パターン
一口に特定技能の在留資格による採用といっても、対象の外国人の居住地や試験の有無などによって受入れまでの流れ、パターンは異なります。ここでは外国人人材を採用できるパターンを4つまとめました。
試験情報のまとめはこちら。
特定技能総合支援サイト「雇用の流れ」
①国内在住→試験合格→就業
日本国内に在留している外国人(留学生など)を採用する場合。このケースでは、まず特定技能1号の在留資格を取得する必要があります。
在留資格を特定技能に変更するには、日本語能力と各分野の技能試験の合格が必要です。
日本語能力試験にはN1~N5(N1が最も難易度が高い)の5段階の難易度が設定されており、特定技能の資格に必要なN4は基本的な日本語が理解できるレベルに該当します。
※介護分野のみ日本語能力試験に加えて独自の日本語試験を受ける必要があります。
②国内在住→試験不要(技能実習修了)→就業
特定技能の在留資格は試験が一部免除される場合があります。
・技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、日本語試験の免除が受けられます。(技能実習1号は不可)
・特定技能のうち従事しようとする業務と技能実習2号の職種や作業に関連性が認められる場合は技能評価試験も免除されます。
技能実習には1号、2号、3号の区分が設けられており、技能実習1号から特定技能への移行には、免除制度は無く技能評価試験を受験し合格する必要があります。
技能実習2号修了した者のうち、上記の条件を満たす者は無試験で特定技能の在留資格へと移行が可能です。
※上記の条件を満たさない場合は試験を受ける必要があります
技能実習3号を修了した者は、実習計画を満了することが必要になります。
③海外在住→試験合格→来日&就業
海外から来日する外国人も試験の必要性の有無によって就労までの流れが異なります。技能実習2号を修了せず入国する外国人の方の場合は、国内在住の留学生などと同じように技能と日本語の試験に合格する必要があります。
海外在住の外国人は国により国外試験も可能であり、日本語試験では国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)を受けます。海外在住の方でも技能試験の目的のために短期滞在ビザを取得して来日し、日本国内で試験を受けることも可能です。
そして無事試験に合格した場合は求職、雇用契約の過程を経て在留資格の取得、来日という流れになります。
④海外在住→試験不要(技能実習修了)→来日&就業
技能実習2号を修了し帰国した外国人の方は、②の条件を満たせば特定技能の在留資格に必要な日本語試験や技能試験を新たに受ける必要はありません。※②の条件を満たさない場合は試験を受ける必要があります。
試験免除にあたる場合、求人募集に直接申し込むか、民間の職業紹介事業者による求職の斡旋によって受入れ機関と雇用契約の締結を行うことができます。
その後、就労する企業から業務の内容や報酬などの労働条件に関する事項、入国に当たっての手続きに関する事項などの情報提供、健康診断などの流れを経て来日、就業となります。実習先が登録支援機関の場合は、在留資格などの手続きも代行してもらうことも可能です。
受入企業が負担する費用
特定技能の在留資格を持った人材を採用する場合、受入企業が負担する費用にはどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは特定技能外国人を採用する際にかかる費用の詳細を解説します。
人材採用にかかる費用
特定技能の在留資格を取得した人材を採用する場合は、いくつか方法があります。
①人材派遣会社からの紹介
人材派遣会社からの紹介で特定技能外国人を採用する方法は、派遣会社へ紹介料を支払う必要があります。
紹介料は各派遣会社によって異なりますが、1人につき特定技能外国人の年収の20-30%程度の紹介料がかかります。
②自社サイトでの募集
自社サイトで募集する場合は紹介手数料などを支払う必要はありません。
③業界団体などの求人サイトの利用
掲載費用の相場は求人サイトや掲載プランなどによって異なりますが、おおむね1ヶ月数万円~30万円ほどです。
また成果報酬制のプランを採用している外国人特化の求人サイトもありますが、この場合は年収の30%~35%が相場となる場合が多いです。
この他、特定技能外国人を採用する際には、法律で定められた支援を行う必要があります。特定技能外国人の支援とは、支援計画の策定、各国大使館への申請、在留資格変更許可申請、雇用契約の変更、事前ガイダンス、空港送迎、居住紹介などのことを指します。
これらの支援を特定技能の知識に乏しい受入れ先企業が行うことは難しいため、大半の企業は登録支援機関と呼ばれる特定技能外国人を支援する機関に委託するのが一般的です。
【登録支援機関一覧】http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html
受入れ先企業はこの委託にかかる費用を毎月支払う必要があります。ちなみに登録支援機関への委託料相場は1か月約2~4万円となっています。
採用以外にかかる費用
・健康診断の費用 約1万円/人
・特定技能ビザの申請費 約15~20万円/人
・1年ごとの在留期間更新申請 2~5万円/人
・(海外在住の特定技能外国人の方を雇用した場合)入国渡航費
・(特定技能試験に合格していない場合)受験料 など
※外国人支援に関する費用を特定技能外国人から徴収することはできません。
送り出しに必要になる教育費や渡航費は、送り出す国の規制やガイドラインを尊守することとされています。よって、国によってこれらの費用の取扱いが変わる場合があります。
入国管理局ガイドラインでは送り出し国のルールに基づき、就労に必要な費用のすべて、もしくは一部を負担することが推奨されています。
採用に関する課題
特定技能外国人を採用する場合は、給与のほかに支援費用がかかったり、面談や試験実施などに時間がかかったり、スケジュールの調整が難しいことなどが課題になっています。
このような理由から現地に赴くのが難しい企業などはWEBでの面接、面談を行うこともあります。WEB面接の場合は渡航する必要がなくなるため、時間と費用の節約が可能です。
ただし、WEB面接の場合は候補者の生活環境、雰囲気、性格などを把握するのが難しいといったデメリットもあることを理解しておかなければなりません。
特定技能人材の雇用後に必要な手続き・書類・提出先
特定技能外国人の雇用後はさまざまな手続きを行う必要があります。また、必要書類や提出先も異なることが多いですので事前にある程度の知識を身に付けておくようにしましょう。ここでは雇用後に必要になる手続きや書類などを解説します。
入管法上の届け出
特定技能外国人の方を雇用すると、受入れ企業は入管法上の届け出を行う必要があります。入管法上の届け出は、特定技能外国人の方と新たに雇用契約を締結したときや変更があったとき、支援計画が変更になったときなどに必要になります。受入れ先企業が入管当局へ提出する書類には、以下のようなものがあります。
| 届出書の種類 | 詳細 |
| 特定技能雇用契約に係る届出書 | 【法務省】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00187.html |
| 支援変更計画に係る届出書 | 【法務省】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00188.html |
| 支援委託計画に係る届出書 | 【法務省】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00189.html |
| 受入れ困難に係る届出書 | 【法務省】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00190.html |
| 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書 | 【法務省】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00194.html |
| 受入れ状況に係る届出書 | 【法務省】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00200.html |
| 支援実施状況に係る届出書 | 【法務省】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00192.html |
| 活動状況に係る届出書 | 【法務省】 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00191.html |
ご覧のように特定技能外国人の方を雇用すると、入管法上の届け出だけでも多くの書類を提出しなければなりません。
特に注意しておきたいのは「受入れ状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出書」「活動状況に係る届出書」です。
これらは変更の有無に関係なく、四半期に1回、3ヶ月に1度の届け出が定められています。なお、上記3種の届け出期間の詳細は以下のとおりです。
| 第1四半期 | 1月1日~3月31日まで |
| 第2四半期 | 4月1日~6月30日まで |
| 第3四半期 | 7月1日~9月30日まで |
| 第4四半期 | 10月1日~12月31日まで |
各企業は翌四半期の初日から14日以内に、企業の住所を管轄する地方出入国在留管理局に上記書類を提出する必要がありますので注意しておきましょう。
ハローワークへの届け出
平成19年10月1日から外国人を雇用した企業は、ハローワーク(厚生労働大臣)へ労働者の氏名や在留資格などについて届け出を行うことが義務付けられました。この届け出は雇用時だけではなく、離職時にも行う必要があります。
届け出の対象となる外国人の範囲は、日本国籍を有さない方で、かつ在留資格が「外交」「公用」以外の方となります。
また特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)の方は、文字通り特別な法的地位が与えられているため、日本国内における活動に制限がありません。
よって特別永住者に該当する方は、外国人雇用状況の届け出制度の対象外となりますので、この場合は届け出を行う必要はなくなります。届け出に記載する事項は、以下の8つです。
| 届け出事項 | 詳細 |
| 氏名 | 本名を記載(通称名は不可) |
| 在留資格 | 在留カードの「在留資格」またはパスポートの上陸許可証印に記載された内容を記入 |
| 在留期間 | 在留カードの「在留資格」またはパスポートの上陸許可証印に記載された内容を記入 |
| 生年月日 | 在留カードまたはパスポートの該当箇所を転記 |
| 性別 | 在留カードまたはパスポートの該当箇所を転記 |
| 国籍・地域 | 在留カードまたはパスポートの該当箇所を転記 |
| 資格外活動許可の有無 | 資格外活動許可を受けて就労する外国人の場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書またはパスポート上の資格外活動許可証印で資格外活動許可の有無、許可の期限、許可されている活動の内容を記入 |
| 在留カード番号 | 在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の番号を記入 |
以上に加え、雇用保険被保険者資格取得届(届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となる場合)もしくは、外国人雇用状況届出書(雇用保険の被保険者とならない外国人の場合)を提出する必要があります。
外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なります。
雇用時のハローワークへの届け出に関する詳細はこちら。
内定を出してから勤務開始までの期間は
内定を出してから勤務開始までにかかる期間や日数は、国内在住か海外在住かによって異なります。
まず国内在住の特定技能外国人の方を雇用する場合は、内定を出してから在留資格変更許可申請を行います。在留資格の変更が認められるまでの期間は、約1ヶ月~3ヶ月ほどです。
一方、海外在住の外国人の方を雇用する場合も特定技能ビザ発行のために「在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があります。在留資格認定証明書の交付にも審査があり、その期間は在留資格変更許可申請と同じく約1ヶ月~3ヶ月です。
ただし、就労系ビザの審査期間は一般的に「認定」の案件が最も長くなりやすいといわれています。
また仮に審査を通過したとしても交付された認定証明書を海外にいる外国人の方に送付し、それを本人が本国の日本領事館などへ提出する必要があります。よって海外在住の外国人の方は、特定技能ビザの発行までに要する日数が国内在住組より延びる可能性が高いです。
在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月ですので、企業はそれまでの間に外国人の方が日本に入国できるように調整をしなければなりません。
また、海外在住の方ですとフライトの手配や来日までにかかる日数も考慮しておく必要があります。
一般的に在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書の交付申請は、毎年2月~5月周辺に審査期間が長くなります。
ですから勤務開始時期が3月や4月と決まっている企業は、特定技能ビザ発行までに要する期間を考慮して、年明け前から必要な準備を進めることを推奨します。
おすすめの採用手法
グローバル人材の採用は必要な手続きが異なるため、国内の人材採用手法では思うような結果が出ない場合も多いと言われています。
では特定技能外国人の方の採用を目指す企業は、どのような方法で人材を探せばよいのか?ここでは特定技能の在留資格を持つ外国人を採用するのにおすすめな手法を解説します。
人材紹介
グローバル人材の需要が高まりを見せているのと同時に、近年は外国人を採用したい企業と働きたい外国人のマッチングを行う人材紹介企業も増加傾向にあります。
特に外国人専門の人材紹介会社は、前述の登録支援機関への登録を済ませていることが多いため、ケースによっては人材紹介と入国後の支援までを一貫して依頼することも可能です。
特定技能外国人の方の採用を目指す企業が人材紹介を利用するメリットは、採用担当者の工数カットや費用面のリスク軽減です。
人材紹介会社を利用すると、採用した人材が入社するまでは手数料が発生しないため、仮に採用できなかった場合の費用面のリスクを抑えることが可能です。
ただし、人材紹介会社の担当者のリサーチ力などが低いと希望する人材像に見合わない人材を紹介される可能性もあります。
また、人材紹介会社にも得意分野と不得意分野がありますので、企業が人材会社を利用する場合は、自社の業種に対応可能か否かという点も確認しておくことが大切です。
求人メディア
求人メディアを活用する方法もおすすめです。
現代社会はインターネット全盛時代ですので、ネット検索をかければ多くの外国人に特化した求人サイトを見つけることができます。
ちなみに求人サイトを比較したい場合は、外国人専門の求人サイトが集ったポータルサイトなどを参考にするのもよいでしょう。特に専門的な求人サイトになると、特定技能外国人の方を雇う際の注意点やポイントなどを解説していることもあります。
これら参考になる情報、貴重になる情報を掲載している求人サイトは外国人の雇用に関する専門的知識を持っている場合が多く、特定技能外国人の方を採用する手法としては安心、安全です。
スカウトサイト
スカウトサイトとは求人サイトや人材紹介サービスにプロフィール(職務経歴など)を登録しておき、そこから求人を希望する企業などから勧誘を受けられるサービスのことを指します。
スカウト機能が充実した求人サイトになると、多数の登録者の中から国籍や日本語レベルなど複数の条件を指定して検索することも可能です。自社でスカウトサイトを利用するメリットは、求める人材像に近い人材を採用できるということです。求める能力や日本語レベルなどの基準を十分に理解しているため、イメージ違いによる採用失敗などを防ぐことが可能です。
スカウトサイトには即戦力候補となる外国人の方も多数登録していますので、人材育成などにかかる手間やコストを極力削減したいといった企業には適した手法ともいえるでしょう。
まとめ
特定技能の在留資格を取得して就労するには、試験合格や入管法上の届け出、ハローワークへの届け出などやらなければならないことが多くあります。
特定技能ビザの発行までにも1ヶ月~3ヶ月ほどの期間を要するため、これから特定技能外国人の方を採用する企業は早めの手続き等を行っておくことをおすすめします。
特定技能の在留資格に関する疑問をお持ちの企業や人材担当者の方はぜひ参考にしてください。
【PR】特定技能人材の中途採用はスキルド・ワーカー

2019年に成立した在留資格「特定技能」により、日本国内に外国人人材の受け入れが始まりました。
特定技能で外国人材を採用する企業が着実に増える中、特定技能人材側の転職希望者も増えてきました。
そもそも特定技能は日本人と同等条件での就業が前提。
日本人がごく普通に転職するように、技能人材に転職希望者が出てくるのは自然な流れと言えます。
特定技能人材の転職希望者の多くは仕事に対するモチベーションは高いものの、職場環境とマッチしていないがゆえに活躍し切れていないケースがほとんどなのが現状です。
スキルド・ワーカーは、丁寧なヒヤリングと面談によるマッチングを最も重視したサービス。
特定技能人材の中途採用にも力を入れています。
こんなお悩みのあるご担当者様におすすめ!
・日本国内だと業界的に人材不足が著しい
・募集をかけても経験者の応募がなかなか来ない。
・採用してもモチベーション維持や育成に手間がかけられない
スキルド・ワーカーは特定技能人材の採用マッチングから住居/ビサの手続きなどの受け入れ準備、採用までフルサポートいたします。
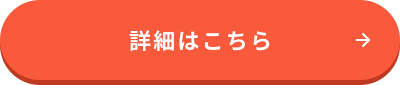
特定技能人材の採用をお考えの皆様へ
今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。
・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
・どのような仕事を任せられるのか?
・どの国の人材が良いのか?
・雇用するにあたり何から始めればよいのか?
…など、様々不安や疑問があるかと思います。
外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。
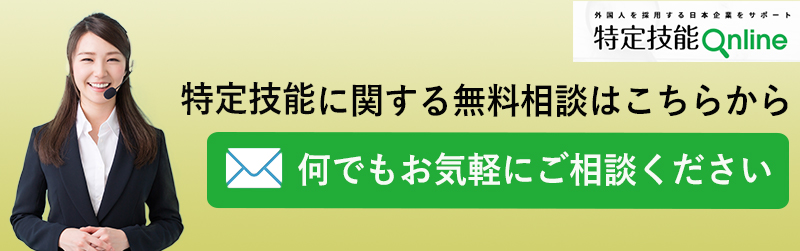


この記事が気に入ったら
いいねをお願いします!
関連記事リンク
-
 特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。
【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。 -
 特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年6月末での特定技能1号における在留外国人数は251,747人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年6月末での特定技能1号における在留外国人数は251,747人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。
特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。 -
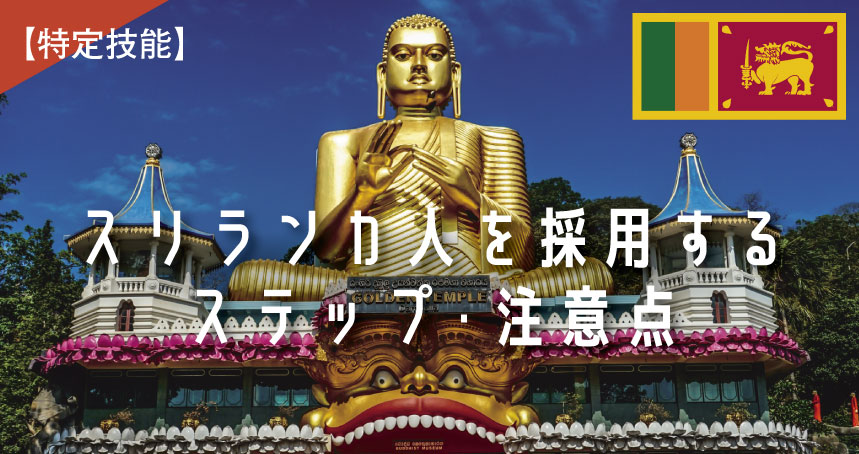 【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。 インド洋の島国、スリランカ。北海道の約8割に相当する大きさで、自然が豊かな様子から「インド洋の真珠」とも呼ばれています。イギリスの植民地時代にはセイロンという国名だったことからも伺えるように紅茶の生産が盛んで、他の主要産業は農業と繊維業。仏教や主食が米であることなど、日本との共通点も多く見られます。そんなスリランカから特定技能労働者を受け入れるポイントを説明していきます。
【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。 インド洋の島国、スリランカ。北海道の約8割に相当する大きさで、自然が豊かな様子から「インド洋の真珠」とも呼ばれています。イギリスの植民地時代にはセイロンという国名だったことからも伺えるように紅茶の生産が盛んで、他の主要産業は農業と繊維業。仏教や主食が米であることなど、日本との共通点も多く見られます。そんなスリランカから特定技能労働者を受け入れるポイントを説明していきます。
セミナー情報
-
 【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。
【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。 -
 造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。
造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。 -
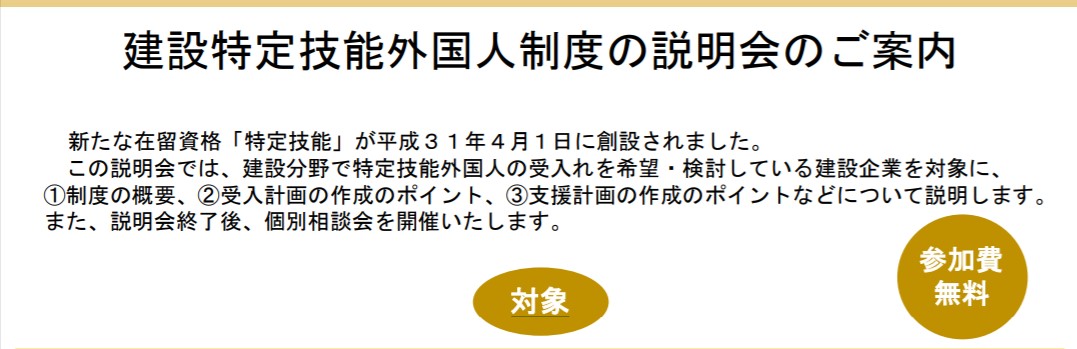 【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。
【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。

-

2025/03/28
特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】
-

2024/11/15
【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。
-

2024/10/04
特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】
-

2024/10/04
特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?
-
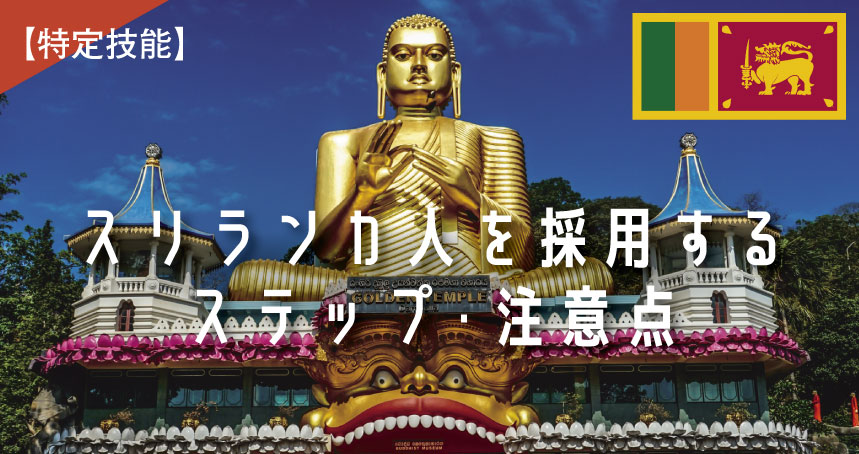
2024/07/31
【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。
-

2024/07/31
【特定技能】ネパール人を採用するステップ・注意点を解説。
-

2024/04/11
特定技能在留外国人数【2023年12月末時点】
-

2024/01/17
特定技能1号在留外国人数【2023年6月末時点】



