特定技能「鉄道」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ
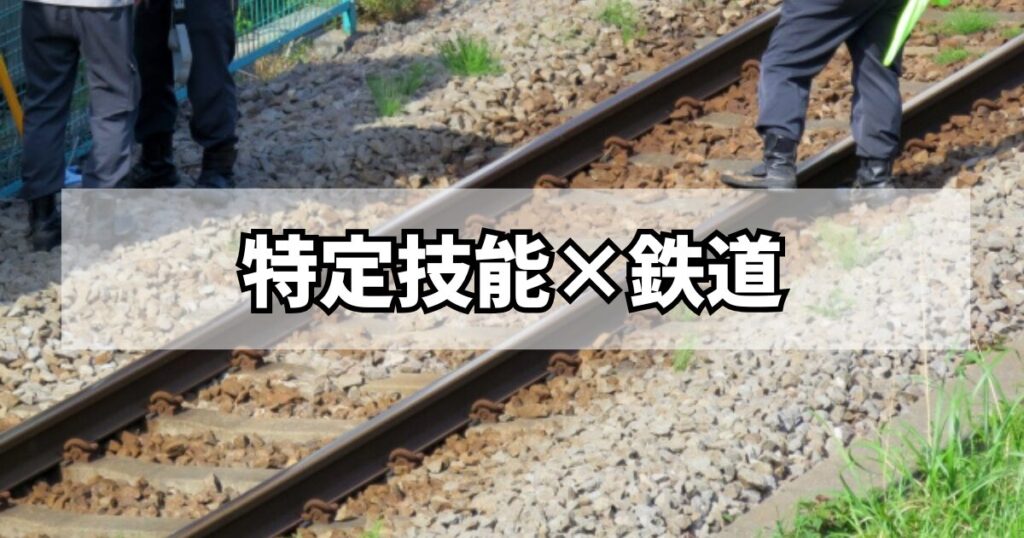
特定技能「鉄道」とは
特定技能とは、人材が不足している特定産業分野において、一定の専門性や技能を持っている外国人材を受け入れる在留資格制度です。全16分野において外国人材の就労が認められていますが、そのうちの1つに「鉄道」があります。制度の新分野として2024年3月に新しく追加されました。
新しく追加されたことにより、運転士や車掌、車両の整備・製造などに従事できる外国人材を受け入れることが可能となりました。これにより、鉄道業界の人手不足の解消が期待されています。
受け入れ見込み人数
政府は、16分野ごとの今後5年間の受け入れ見込み人数(令和6年4月から)を定めており、鉄道の分野は1,000人が見込まれています。
日本の鉄道業界は、高度な技術と安全性で世界的に評価されていますが、その裏には膨大な人手による日々の維持管理作業があります。軌道や電気設備、車両の整備など、定期的な保守作業は安全な運行に欠かせません。
しかし、専門的な業務が多いことから参入者はあまり多くなく、慢性的な人手不足が問題となっています。専門的な知識や技能を備えている外国人材を受け入れることは、業界の問題解決・さらなる発展のきっかけとなるでしょう。
受け入れられた外国人材は、主に以下のような業務に従事させることが可能です。
| 業務区分 | 従事可能な業務 |
| 軌道整備 | ・軌道検測作業 ・レール交換作業 ・まくらぎ交換作業 ・バラストを取り扱う作業 ・保安設備を取り扱う作業等 ・事務作業 ・作業場所の整理整頓や清掃 |
| 電気設備整備 | ・電路設備 ・変電所等設備 ・電気機器等設備 ・信号保安設備 ・保安通信設備 ・踏切保安設備 ・事務作業 ・作業場所の整理整頓や清掃 |
| 車両整備 | ・列車検査、定期検査、臨時検査 ・構内入換 ・駅派出対応 ・改造工事 ・定期・臨時清掃業務 ・在庫・予備品管理、工場設備取扱い ・事務作業 ・作業場所の整理整頓や清掃 |
| 車両製造 | ・素材加工 ・部品組立て作業 ・構体組立て ・塗装 ・溶接 ・ぎ装 ・台車枠製造 ・台車組立て ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・試験・検査 ・部品検収・配膳業務 ・事務作業 ・作業場所の整理整頓や清掃 |
| 運輸係員 | ・ポイント操作 ・入換え合図 ・駅設備管理・取扱業務 ・旅客案内・貨物取扱業務 ・運行管理業務 ・車掌業務 ・運転士業務 ・事務作業 ・作業場所の整理整頓や清掃 |
参照:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
鉄道業界の現状
鉄道は人々の生活や経済活動を支えていますが、業界内では深刻な人手不足という大きな課題に直面しています。とくに運転士が不足してしまうと、列車の運行本数を減らしたり、最終列車の時刻を繰り上げたりなどの措置を取らざるを得ない状況となってしまいます。
ここからは業界の現状や人手不足の原因について解説します。
若年層の減少によって人手不足が深刻化
鉄道分野は慢性的な人手不足に陥っており、年々深刻になっています。国土交通省の「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」によると、平成初期は鉄道事業者の職員が27万人以上いましたが、令和に入ってからは約19万人まで減っています。
また、ただ人手が不足しているだけではなく、若年層の減少も問題です。業界内の従事者は高齢化が進んでおり、定年を迎えようとしている現場の熟練労働者も多くなっています。しかし、若年層の定着・参入は少なく、次世代の業界を担う人材が確保できていません。
鉄道業界は、不規則なシフト制での労働や夜間作業など厳しい環境で働いている傾向にあります。それだけ厳しい労働環境にも関わらず、賃金は一般的な企業とそれほど変わらないため、敬遠する若者が増えているようです。
今後さらにインフラ整備需要の増加が推察されている
鉄道分野は、今後さらにインフラ整備・既存施設の更新需要の増加が推察されています。新しい路線の建設や老朽化した設備の修繕・改良が今後さらに増加していくでしょう。しかし、現状ではこれらに対応する人材が不足し、今後の高まる需要に十分に対応ができません。
また、近年では訪日外国人観光客の増加によって鉄道利用者は増加しており、需要はより高まっていきます。そのため、安全で効率的な運行を支えるための人材確保が急務となっています。
このような懸念される問題が多いなかで、「外国人材の雇用」による人材確保を目指すための取り組みが特定技能制度です。日本国内に限定することなく、幅広い人材の採用・雇用を進めていくことが可能となります。
特定技能「鉄道」の取得要件
特定技能「鉄道」を取得するには、一定業務をこなせる水準の外国人材であることを証明しなければいけません。また、受け入れる企業側も要件を満たす必要があります。
ここからは取得の要件について解説します。
業務区分によって異なる「評価試験」と「日本語試験」の合格が必要
特定技能「鉄道」の取得には、各業務区分の「評価試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。
評価試験は各業務区分によって分かれており、必要な知識や経験を備えていることを確認するための試験となっています。従事する業務に連動した試験内容となっており、運輸係員であれば安全運行に必要な知識や旅客対応の基本スキル、軌道整備であれば線路や軌道部品の取り扱い方法や作業をおこなううえでの安全に関するポイントなどが出題されます。試験日や試験会場もそれぞれ異なります。
日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験」のどちらかに合格する必要があります。日本語能力試験はN1からN5までありますが、運輸係員のみ日本語能力試験「N3」(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベル)以上、それ以外は「N4」(基本的な日本語を理解することができるレベル)が必要です。
運輸係員のみ日本語能力の基準が高く設定されているのは、業務内容が大きく関係します。運輸係員の業務は、運輸指令とのコミュニケーションや乗客への対応などを要する業務です。また、万が一の事態において、異常時の避難誘導や運輸司令との迅速なやり取りなど緊急対応が求められるため、他の業務区分よりも厳しい日本語能力が求められます。
特定所属機関(受入れ企業)の要件
人材を受け入れる機関は、以下の要件を満たす必要があります。
参照:鉄道分野|出入国在留管理庁
- 鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者、鉄道事業または軌道事業のに関する事業経営者、車両の整備または車両の製造に関わる事業経営者であること。
- 「鉄道分野特定技能協議会」の構成員になること。
- 協議会に対して必要な協力をおこなうこと。
- 国土交通省または委託を受けた者が行う調査・指導に対し、必要な協力をおこなうこと。
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合、協議会・国土交通省に対し必要な協力を実施する機関に委託すること。
特定技能制度の活用を検討している企業は、まずこれらの条件を整備し、計画的な受け入れ体制を構築することが重要です。
特定所属機関(受入れ企業)の注意点
特定技能人材を雇い入れる際には、いくつか注意点があります。ここからは、特定所属機関(受入れ企業)の注意点を解説します。
鉄道分野特定技能協議会への加入が必須
企業が特定技能人材を受け入れる際、「協議会への加入」が義務付けられています。
鉄道分野の特定技能協議会は国土交通省が設立しており、外国人材の受入れにともなう多様な課題を解決したり、企業と労働者双方が安心して働ける環境を整えたりするために運営されています。加入後は、協議会の取り組みへの協力が求められます。
加入は、ビザ申請の前までにおこなう必要があります。ビザ申請の際には、協議会の加入証明書を原則提出しなければいけません。そのため、加入申請が遅れるとビザ申請ができません。人材の採用を決めたら、できるだけ早めの申請をおこなうようにしましょう。
技能実習2号からの移行が可能な区分がある
軌道整備・車両整備・車両製造の3つは、技能実習2号からの移行も可能となっています。以下の技能実習2号を良好に終了した場合は、試験が免除となります。
| 業務区分 | 職種 | 作業 |
| 軌道整備 | 鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 |
| 車両整備 | 鉄道車両整備 | 走行装置検修・解ぎ装 |
| 空気装置検修・解ぎ装 | ||
| 車両整備 | 機械加工 | 普通旋盤 |
| フライス盤 | ||
| 数値制御旋盤 | ||
| マシニングセンタ | ||
| 金属プレス加工 | 金属プレス | |
| 鉄工 | 構造物鉄工 | |
| 仕上げ | 治工具仕上げ | |
| 金型仕上げ | ||
| 機械組立仕上げ | ||
| 電子機器組み立て | 電子機器組み立て | |
| 電気機器組み立て | 回転電機組立て | |
| 変圧器組立て | ||
| 配電盤・制御盤組立て | ||
| 開閉制御器具組立て | ||
| 回転電機巻線製 | ||
| 塗装 | 金属塗装 | |
| 噴霧塗装 | ||
| 手溶接 | ||
| 半自動溶接 |
義務的支援を実施する
日本に初めて到着する外国人材は、日本の文化や暮らし方に慣れていないことがほとんどです。そのため、労働面でも生活面でも必要な支援をおこなう必要があります。
これは「義務的支援」として、企業が必ず提供しなければならない支援です。住居の確保や各種手続きのサポート、日本で生活するうえで必要な情報の提供、日本語学習の機会の提供など、問題なく日本で生活ができるように支援をしていきましょう。
自社でおこなうのが大変な場合は、「登録支援機関」に委託するのも一つの手です。登録支援機関は、外国人材の雇用に必要な手続きや支援業務を代行する専門機関です。委託することで外国人材への支援を代行しておこなってくれるので、自社の負担を大幅に減少させることが可能です。
試験の受講方法
先ほども触れたように、評価試験は各業務区分によって内容が異なります。運営元や試験会場も異なるので、各運営のホームページを確認するようにしてください。
| 業務区分 | 運営元・問い合わせ先 | 試験に関するホームページ |
| 軌道整備 | 一般社団法人 日本鉄道施設協会:03-5846-5300 | https://www.jrcea.or.jp/tokuteiginou/ |
| 電気設備整備 | 一般社団法人 鉄道電業安全協会:03-5688-5494 | https://www.railecr.com/news/20241101.html |
| 車両整備 | 一般社団法人 日本鉄道車両機械技術協会:03-3593-5611 | https://www.rma.or.jp/ssw/index.html |
| 車両製造 | 一般社団法人 日本鉄道車輌工業会:03-3257-1901 | https://www.tetsushako.or.jp/specific_skills.html |
| 運輸係員 | 一般社団法人 日本鉄道運転協会:03-3837-2401 | 試験に関するホームページは準備中 |
ただし、実施方法については、いずれもコンピュータを使用して実施する「CBT方式」か「ペーパーテスト方式」によって実施されます。また、各業務に関連する「学科試験」と、図やイラストなどを用いた状況設定において正しい判別、判断をおこなえるかチェックする「実技試験」が主な内容となるようです。
制度に関する情報の更新や変更は、国土交通省のホームページにも随時掲載されます。受験を希望する方や、制度について詳細をチェックしたい方は、こまめに確認するようにしてください。
特定技能人材の採用をお考えの皆様へ
今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。
・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
・どのような仕事を任せられるのか?
・どの国の人材が良いのか?
・雇用するにあたり何から始めればよいのか?
…など、様々不安や疑問があるかと思います。
外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。

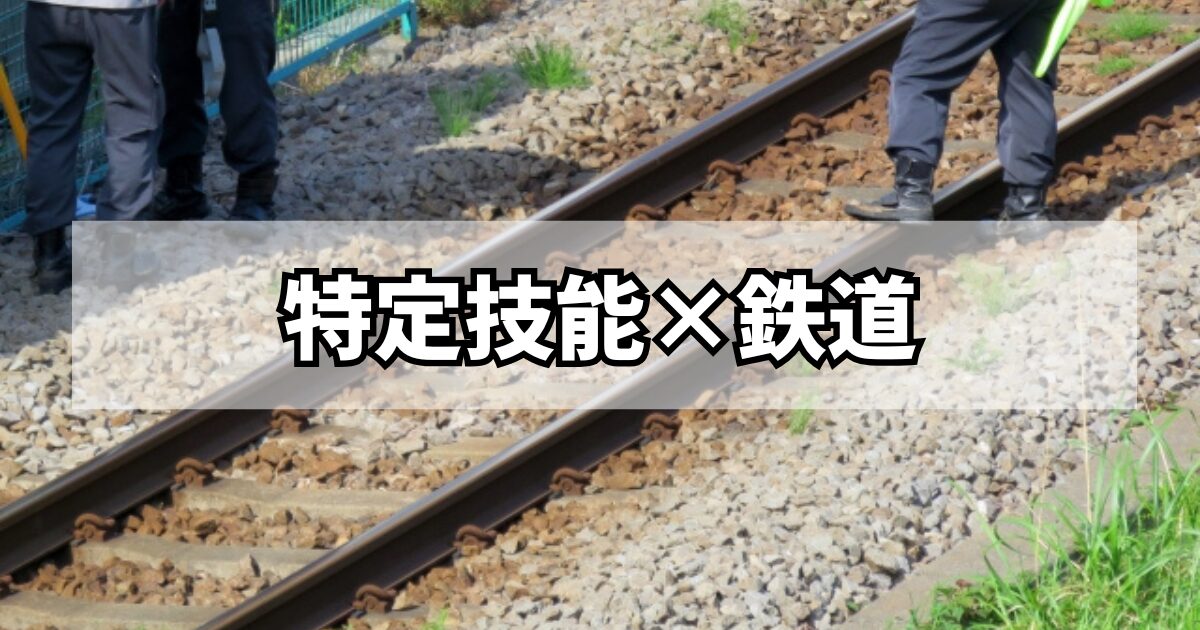
この記事が気に入ったら
いいねをお願いします!
関連記事リンク
-
 特定技能「林業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「林業」は、深刻な人手不足に悩む業界の救世主となる制度です。本記事では、制度の概要、受け入れ要件、試験内容、企業側の注意点までを詳しく解説します。
特定技能「林業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「林業」は、深刻な人手不足に悩む業界の救世主となる制度です。本記事では、制度の概要、受け入れ要件、試験内容、企業側の注意点までを詳しく解説します。 -
 特定技能「自動車運送業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 特定技能「自動車運送業」は、2024年3月に新設された在留資格で、深刻な人手不足が続く運送業界において外国人ドライバーの受け入れが可能になります。本記事では、制度の概要から受け入れに必要な準備、取得要件や注意点まで詳しく解説します。
特定技能「自動車運送業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 特定技能「自動車運送業」は、2024年3月に新設された在留資格で、深刻な人手不足が続く運送業界において外国人ドライバーの受け入れが可能になります。本記事では、制度の概要から受け入れに必要な準備、取得要件や注意点まで詳しく解説します。 -
 特定技能「木材産業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「木材産業」分野では、外国人材の受け入れが可能となりました。人手不足や高齢化が進む業界で、専門技能を持つ人材の活用が注目されています。取得要件や業務内容も解説。
特定技能「木材産業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「木材産業」分野では、外国人材の受け入れが可能となりました。人手不足や高齢化が進む業界で、専門技能を持つ人材の活用が注目されています。取得要件や業務内容も解説。 -
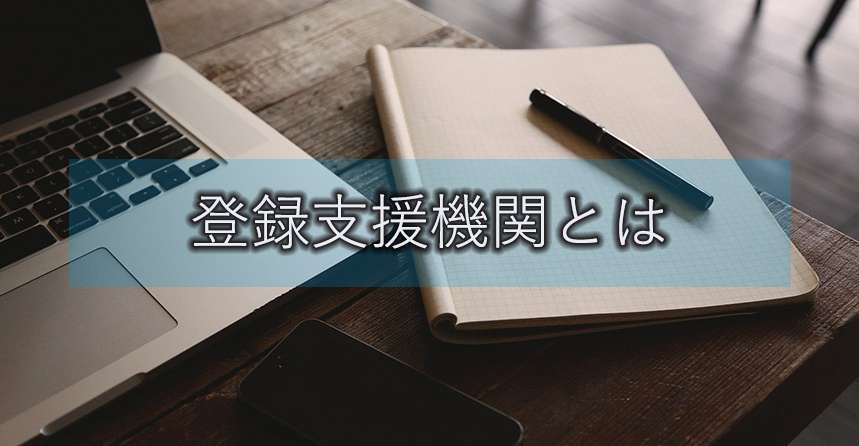 「登録支援機関」とは?特定技能制度における登録支援機関の役割・選び方、取得条件や注意 みなさんは「登録支援機関」という組織をご存知でしょうか。外国人労働者を雇っている方は、この組織名を耳にしたことがあるかもしれません。これから外国人労働者を雇いたいと考えている方は、この「登録支援機関」を上手に利用していくことが大切になります。今回は、この登録支援機関について、役割や業務、選び方などの詳細情報を紹介していきます。
「登録支援機関」とは?特定技能制度における登録支援機関の役割・選び方、取得条件や注意 みなさんは「登録支援機関」という組織をご存知でしょうか。外国人労働者を雇っている方は、この組織名を耳にしたことがあるかもしれません。これから外国人労働者を雇いたいと考えている方は、この「登録支援機関」を上手に利用していくことが大切になります。今回は、この登録支援機関について、役割や業務、選び方などの詳細情報を紹介していきます。 -
 特定技能「外食」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 外食業における特定技能制度について解説します。
特定技能「外食」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 外食業における特定技能制度について解説します。
コラム情報
-
 特定技能1号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能における在留外国人数は336,196人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能1号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能における在留外国人数は336,196人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 特定技能2号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能2号における在留外国人数は3,073人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能2号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能2号における在留外国人数は3,073人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。
特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。 -
 特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。
【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。
セミナー情報
-
 【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。
【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。 -
 造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。
造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。 -
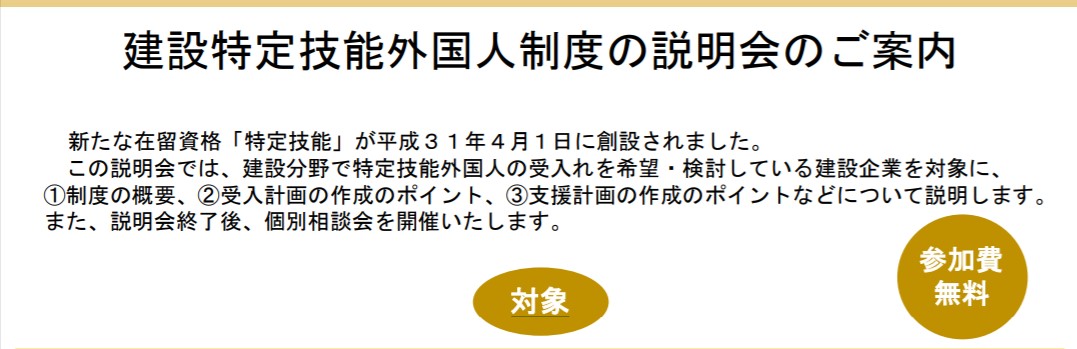 【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。
【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。

-

2025/10/06
特定技能1号 在留外国人数【2025年6月末時点】
-

2025/10/06
特定技能2号 在留外国人数【2025年6月末時点】
-

2025/07/27
特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?
-

2025/03/28
特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】
-

2024/11/15
【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。
-

2024/10/04
特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】
-
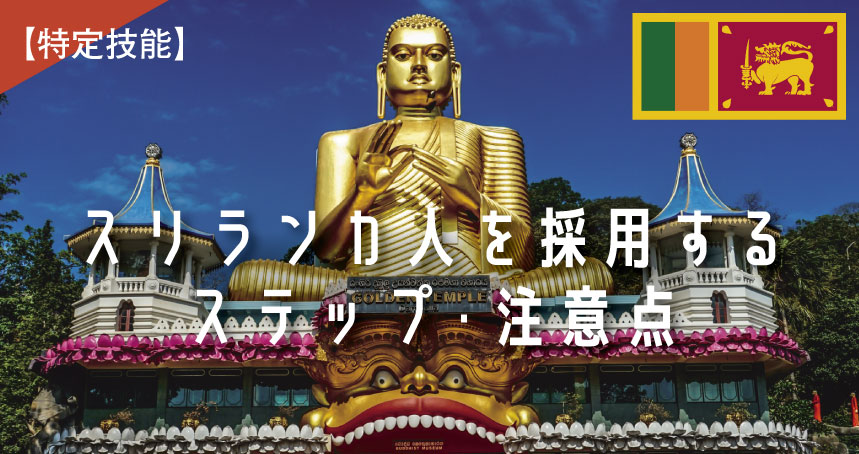
2024/07/31
【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。
-

2024/07/31
【特定技能】ネパール人を採用するステップ・注意点を解説。


