特定技能「自動車運送業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ

特定技能「自動車運送業」とは
特定技能とは、人材が不足している特定産業分野において、一定の専門性や技能を持っている外国人材を受け入れる在留資格制度です。
特定技能制度は全16分野において外国人材の就労が認められていますが、そのなかの1つに「自動車運送業」があります。新分野として2024年3月に新しく追加されました。新しく追加されたことにより、トラック・タクシー・バスの運転手の業種で外国人材を受け入れることが可能となりました。
この制度を適切に活用すれば、即戦力となる人材を確保し、長期的に安定した事業運営が可能になります。
受け入れ見込み人数
政府は、16分野ごとの今後5年間の受け入れ見込み人数(令和6年4月から)を定めており、自動車運送業の分野は24,500人が見込まれています。
自動車運送業界の従事者数は年々減少しており、深刻な人手不足に陥っています。日本は労働人口の減少が著しく、もはや国内だけの人材では対応しきれなくなっているのです。そんななかで、専門的な知識や技能を備えている外国人材を受け入れられる制度を活用できることは、業界の人手不足を解決するきっかけとなるでしょう。
受け入れられた外国人材は、主に以下のような業務に従事させることが可能です。
| 業務区分 | 従事可能な業務 |
| バス運転者 | ・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等) ・接遇業務(乗客対応等) ・車内清掃作業 ・営業所内清掃作業 ・運賃精算、管理 ・その他、主たる業務に付随しておこなう作業 |
| タクシー運転者 | ・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等) ・接遇業務(乗客対応等) ・車内清掃作業 ・営業所内清掃作業 ・運賃精算、管理 ・その他、主たる業務に付随しておこなう作業 |
| トラック運転者 | ・運行業務(運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成等) ・荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等) ・車内清掃作業 ・洗車作業 ・営業所内清掃作業 ・その他、主たる業務に付随して行う作業 |
参照:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
運送業界の現状
運送業界の人手不足は非常に深刻で、最近では時間外労働に関する法改正がおこなわれたことで今後さらに深刻化していくことが推察されています。ここからは運送業界の現状や人手不足の原因について解説します。
日本人ドライバーの人手不足
先ほども触れましたが、日本の自動車運送業界は深刻な人手不足に直面しています。
内閣府が発表している「物流業の人手不足問題」のデータによると、2000年には97.3万人ものトラック運転手の就業者数が存在していました。しかし、2020年には77.9万人となっており、20年で約20万人も就業者が減っています。
ドライバー職は、労働時間が長い一方で、給与水準が全産業平均よりも低い状況にあります。労働人口の減少も人手不足の原因の1つではありますが、条件や待遇がよくないことで、人材の参入・定着が進まないことも原因であるといえます。
また、道路貨物運送業の年齢構成のデータによると、2022年には就業者の約57%が40〜50代であり、20〜30代の若年層は約23%にとどまっています。このような年齢構成の偏りと若年層の少なさは、将来的な労働力不足を一層深刻にさせる要因となるでしょう。
「2024年問題」の対応が必須
自動車運送業界では、「2024年問題」も懸念されています。2024年問題とは、働き方改革法案によってドライバーの労働時間に上限が課されることで発生する問題のことです。
これまでドライバー職の労働環境は、長時間労働の慢性化という課題を抱えていました。そんな労働環境を変えるために法改正をおこない、時間外労働時間を年間960時間に制限しました。
一見、働きやすくなるきっかけになるように思われますが、この法改正によって多くの問題が生じると懸念されています。
1つ目は、1日の積載量が減る可能性があります。労働時間の上限規制に伴い、稼働時間が制限されることで、物流・運送事業者は配送能力の低下を余儀なくされます。これにより、顧客からの受注に対する対応が難しくなり、売上の減少が懸念されます。また、積載量が減ると、同じ配送量を確保するためにはより多くのトラックが必要となり、運行コストが増加してしまうでしょう。これらの要因が相まって、運送・物流業者の売上・利益は減少し、企業の持続可能性にも悪影響を及ぼす要因となります。
2つ目は、企業の売上、利益が減少することで、労働者たちの給与にも影響が出るおそれがあります。従来と同水準の給与を保証できなくなれば、ドライバーの離職が進んだり、新しい人材が集まらなかったりなど、さらなる人材不足に拍車がかかる可能性が高いです。
特定技能「自動車運送業」の取得要件
特定技能「自動車運送業」を取得するには一定業務をこなせる水準の外国人材であることを証明しなければいけません。また、受け入れる企業側も要件を満たす必要があります。
ここからは取得の要件について解説します。
業務区分によって試験が分けられる
取得するには、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。
評価試験は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために、必要な知識や経験を備えていることを確認するための試験です。トラック・タクシー・バスにそれぞれ試験が分けられています。学科試験と実技試験の正答率がいずれも60%以上(学科30問中18問、実技20問中12問が正解)で合格です。
試験の形式は、テストセンターにてコンピュータを使用して実施する「CBT方式」か、申請人(法人)が希望する会場で試験を実施する「出張方式」でおこなわれます。ただし、出張方式はまとまった受験者数がある企業・団体からの申請があった場合のみ実施されます。
日本語試験は、業務区分によって合格が必要となる試験が異なります。
| トラック | 下記のいずれか ・日本語能力試験N4以上 ・国際交流基金日本語基礎テスト |
| タクシー | 日本語能力試験N3以上 |
| バス |
日本語能力試験はN1からN5まであり、N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベル」、N4は「基本的な日本語を理解することができるレベル」です。
タクシーやバスは運行業務以外に乗客とのコミュニケーションやサービス対応が求められますので、より高い日本語能力が求められます。業務区分によって求められる日本語スキルが異なるので注意しましょう。
特定所属機関(受入れ企業)の要件
特定技能「自動車運送業」の人材を受け入れる特定所属機関(受入れ企業)は、以下の要件を満たす必要があります。
国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること。協議会に対し必要な協力をおこなうこと。国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力をおこなうこと。道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業を経営する者であること。一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者であること。新任運転者研修を実施すること。
参照:自動車運送業分野
特定技能制度の活用を検討している企業は、まずこれらの条件を整備し、計画的な受け入れ体制を構築することが重要です。もし要件を満たさずに採用・雇用をおこなうと、企業が罰則を受けることになるので注意が必要です。
特定技能外国人の運転免許の取得ルール
特定技能「自動車運送業」として日本で働くためには、日本の運転免許証も必要となります。
運転免許証は、日本の自動車教習所で教習を受けて取得するか、母国で取得した免許を日本の免許に切り替えるかによって取得します。
母国で取得した免許を日本の免許に切り替える手続きは「外免切替」と呼ばれ、外国の運転免許証を日本での運転を法的に許可された運転免許証に切り替えることが可能です。ただし、外国の運転免許証を取得後、取得国での滞在が通算して3ヶ月以上なければ外免切替はおこなえないので注意しましょう。
特定所属機関(受入れ企業)の注意点
特定技能人材を雇い入れる際には、おさえておくべき注意点がいくつかあります。ここからは、特定所属機関(受入れ企業)の注意点を解説します。
自動車運送業分野特定技能協議会への加入が必須
企業が特定技能人材を受け入れるには、多くの準備・手続きが必要です。その1つとして「協議会への加入」が義務付けられています。
自動車運送業分野の特定技能協議会は国土交通省が設立しており、外国人材の受入れにともなう多様な課題を解決したり、企業と労働者双方が安心して働ける環境を整えたりするために運営されています。加入後は、外国人材受け入れの状況報告や課題の把握、適正な雇用のための情報共有などの活動への協力が必要です。
協議会への加入は、ビザ申請の前までにおこなう必要があります。ビザ申請の際には、協議会の加入証明書を原則提出しなければいけません。そのため、加入申請が遅れるとビザ申請ができません。人材の採用を決めたら、できるだけ早めの申請をおこなうようにしましょう。
新任運転者研修を実施する
タクシー運送業・バス運送業に従事する外国人材を受け入れる場合は、新任運転者研修を実施しなければいけません。
新任運転者研修とは、事業用自動車を運転する際の心構えや、業務に従事する上で必要な技能・知識の修得を目的とした研修です。国土交通省は、新任運転者研修の概要を以下のように定義しています。
新任運転者研修は、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項、第2項及び第5項並びに第39条に規定する事項についての、指導、監督及び特別な指導を受け、並びに適性診断を受診することをいいます。
引用:特定技能Q&A
具体的には、・座学研修(法令、接遇、地理、安全に関する研修)・路上走行研修・適性診断を行うこととしています。
また、新任運転者研修の修了は、業界団体が定めた効果測定の基準に基づき判定されます。
日本の交通マナーを熟知していなければ、危険な事故につながるおそれがあります。事故を発生させてしまうと、企業としても大きな損害を被ることになるので、責任を持って新任運転者研修を実施するようにしてください。
義務的支援を実施する
日本に初めて到着する外国人材は、日本の文化や暮らし方に慣れていないことがほとんどです。そのため、労働面でも生活面でも必要なサポートをおこなうことが大切です。
これは「義務的支援」として、企業が必ず提供しなければならない支援です。住居の確保や各種手続きのサポート、日本で生活するうえで必要な情報の提供、日本語学習の機会の提供など、問題なく日本で生活ができるように支援をしていきましょう。
自社でおこなうのが大変な場合は、「登録支援機関」に委託するのも一つの手です。登録支援機関は、外国人材の雇用に必要な手続きや支援業務を代行する専門機関です。専門的な知識と対応が求められるため、予想以上に負担となることもありますが、登録支援機関へ委託することで外国人材への支援を代行しておこなってくれます。
試験の受講方法
評価試験を受験するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 試験受験日において、満17歳以上である(インドネシアでの試験では満18歳以上)
- 日本または外国で取得した有効な自動車運転免許を保有している
- 日本国籍を有しない
- 在留資格を有している
- 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限のある機関の発行した旅券を所持していない者でない
試験の形式は、テストセンターにてコンピュータを使用して実施する「CBT方式」か、申請人(法人)が希望する会場で試験を実施する「出張方式」でおこなわれます。
CBT方式には決まった受験日は設けられておらず、テストセンターに空きがあれば随時受験が可能です。試験の申請をおこなうと、実施可能な日時を確認できるようになります。
出張方式はまとまった受験者数がある企業・団体からの申請があった場合のみ実施されます。また、日本以外の国でも、インドネシアやタイ、ネパールなどさまざまな場所で出張試験が実施されます。日本と、日本以外の国では受験料が異なるので注意しましょう。
| 受験料(日本国内での実施) | 5,000円(税抜) |
| 受験料(海外での実施) | 37米ドル |
| 証明書発行手数料 | 14,000円(税抜) |
試験の情報については、「一般財団法人日本海事協会 交通物流部 特定技能試験担当」のホームページにて随時発表されます。受験を希望する方や、試験の申請方法について詳しく知りたい方は、ホームページを確認してください。
また、試験用テキストや過去問は公開されていませんが、以下のサイトに試験に関連するテキストが掲載されています。
特定技能人材の採用をお考えの皆様へ
今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか。
・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
・どのような仕事を任せられるのか?
・どの国の人材が良いのか?
・雇用するにあたり何から始めればよいのか?
…など、様々不安や疑問があるかと思います。
外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。


この記事が気に入ったら
いいねをお願いします!
関連記事リンク
-
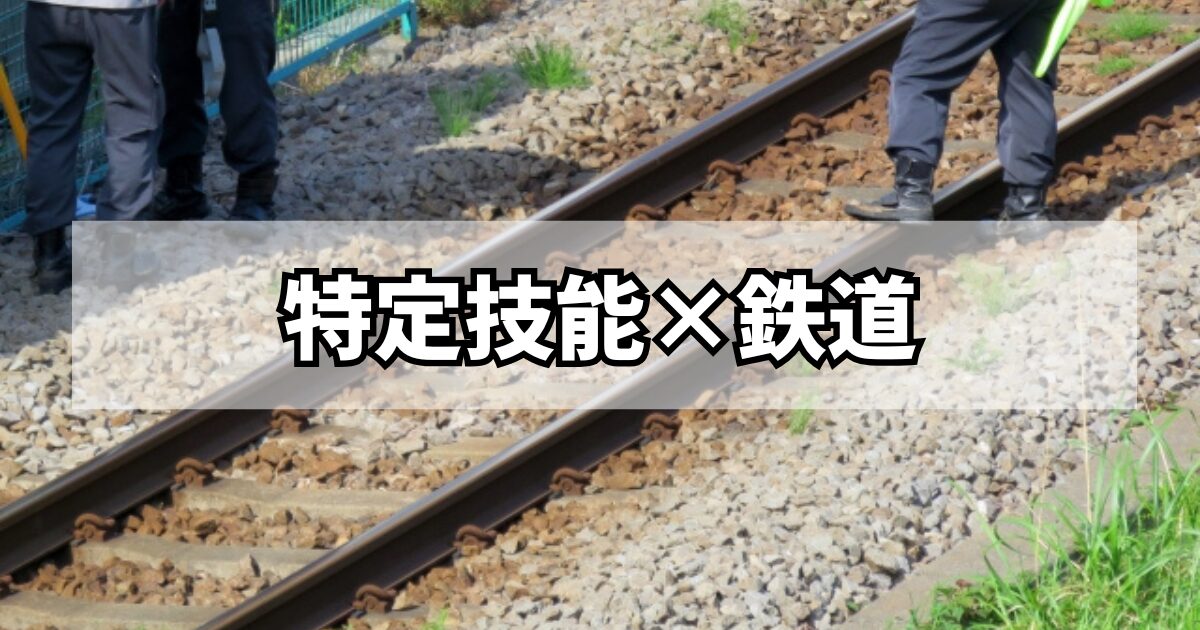 特定技能「鉄道」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「鉄道」分野では、外国人が鉄道業界で働く道が開かれました。業務内容や取得要件、人手不足の背景、企業側の受け入れ体制について詳しく解説します。
特定技能「鉄道」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「鉄道」分野では、外国人が鉄道業界で働く道が開かれました。業務内容や取得要件、人手不足の背景、企業側の受け入れ体制について詳しく解説します。 -
 特定技能「林業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「林業」は、深刻な人手不足に悩む業界の救世主となる制度です。本記事では、制度の概要、受け入れ要件、試験内容、企業側の注意点までを詳しく解説します。
特定技能「林業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「林業」は、深刻な人手不足に悩む業界の救世主となる制度です。本記事では、制度の概要、受け入れ要件、試験内容、企業側の注意点までを詳しく解説します。 -
 特定技能「木材産業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「木材産業」分野では、外国人材の受け入れが可能となりました。人手不足や高齢化が進む業界で、専門技能を持つ人材の活用が注目されています。取得要件や業務内容も解説。
特定技能「木材産業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 2024年に新設された特定技能「木材産業」分野では、外国人材の受け入れが可能となりました。人手不足や高齢化が進む業界で、専門技能を持つ人材の活用が注目されています。取得要件や業務内容も解説。 -
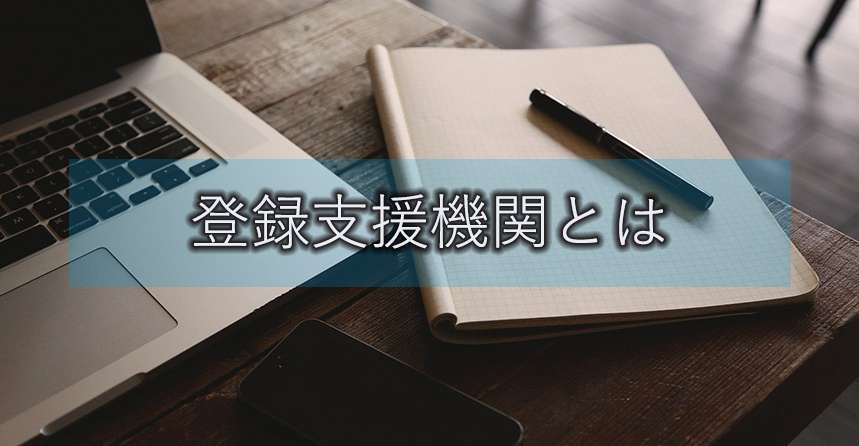 「登録支援機関」とは?特定技能制度における登録支援機関の役割・選び方、取得条件や注意 みなさんは「登録支援機関」という組織をご存知でしょうか。外国人労働者を雇っている方は、この組織名を耳にしたことがあるかもしれません。これから外国人労働者を雇いたいと考えている方は、この「登録支援機関」を上手に利用していくことが大切になります。今回は、この登録支援機関について、役割や業務、選び方などの詳細情報を紹介していきます。
「登録支援機関」とは?特定技能制度における登録支援機関の役割・選び方、取得条件や注意 みなさんは「登録支援機関」という組織をご存知でしょうか。外国人労働者を雇っている方は、この組織名を耳にしたことがあるかもしれません。これから外国人労働者を雇いたいと考えている方は、この「登録支援機関」を上手に利用していくことが大切になります。今回は、この登録支援機関について、役割や業務、選び方などの詳細情報を紹介していきます。 -
 特定技能「外食」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 外食業における特定技能制度について解説します。
特定技能「外食」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ 外食業における特定技能制度について解説します。
コラム情報
-
 特定技能1号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能における在留外国人数は336,196人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能1号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能における在留外国人数は336,196人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 特定技能2号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能2号における在留外国人数は3,073人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能2号 在留外国人数【2025年6月末時点】 出入国在留管理庁は、2025年6月末での特定技能2号における在留外国人数は3,073人(速報値)と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。
特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは? 2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。全14業種にて特定技能人材を受け入れると発表されていますが、今回は工業製品製造業の特定技能制度について紹介いたします。 -
 特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。
特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】 出入国在留管理庁は、2024年12月末での特定技能1号における在留外国人数は284,466人と発表しました。特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標は34万5150人と定められています。国別・業種別の受け入れ人数をまとめました。 -
 【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。
【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。 インドとミャンマーに挟まれる南アジアの国、バングラデシュ。日本の4割ほどの国土に日本人口の1.3倍ほどの約1億7000万人が暮らしています。アジア最貧国と知られ、洪水など災害の多い地域では現在も貧困世帯が多い一方、主に衣料・縫製産業の著しい発展により近年のGDP年間成長率は7.1%(2022年度、バングラデシュ統計局)。平均年齢27.6歳と若く、厳しい環境で培われたハングリー精神に溢れるバングラデシュ人が、日本で活躍する人材として今注目を集めています。
セミナー情報
-
 【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。
【オンラインセミナー】 外国人活躍支援サミット~次世代日本人とつくる日本の未来~ 外国人雇用協議会 外国人雇用協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。 そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、③外国人への教育推進、を展開しています。 本サミット第1日(10月6日)は、約2,000人以上の外国人雇用やサポートに関心のある方に受講いただき、各分野のスペシャリストが登壇する基調講演・パネルディスカッションから学んでいただく機会を提供いたします。 -
 造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。
造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会のご案内 国土交通省及び一般財団法人日本海事協会 からの情報を掲載します。 3月に開催される特定技能制度「造船・舶用工業」に関する説明会のご案内です。 -
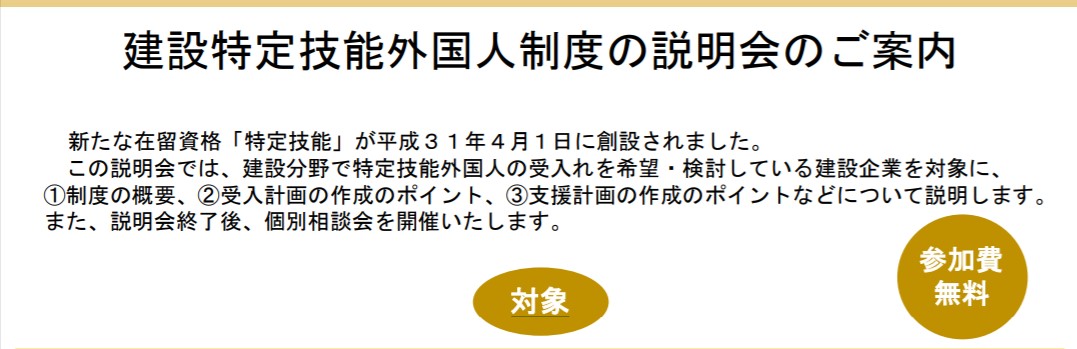 【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。
【一般社団法人建設技能人材機構(JAC) 】建設特定技能外国人制度の説明会 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの情報を掲載します。 2月~3月に開催される特定技能制度「建設業」に関する説明会のご案内です。

-

2025/10/06
特定技能1号 在留外国人数【2025年6月末時点】
-

2025/10/06
特定技能2号 在留外国人数【2025年6月末時点】
-

2025/07/27
特定技能「工業製品製造業」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ・注意点とは?
-

2025/03/28
特定技能在留外国人数【2024年12月末時点】
-

2024/11/15
【特定技能】バングラデシュ人を採用するステップ・注意点を解説。
-

2024/10/04
特定技能在留外国人数【2024年6月末時点】
-
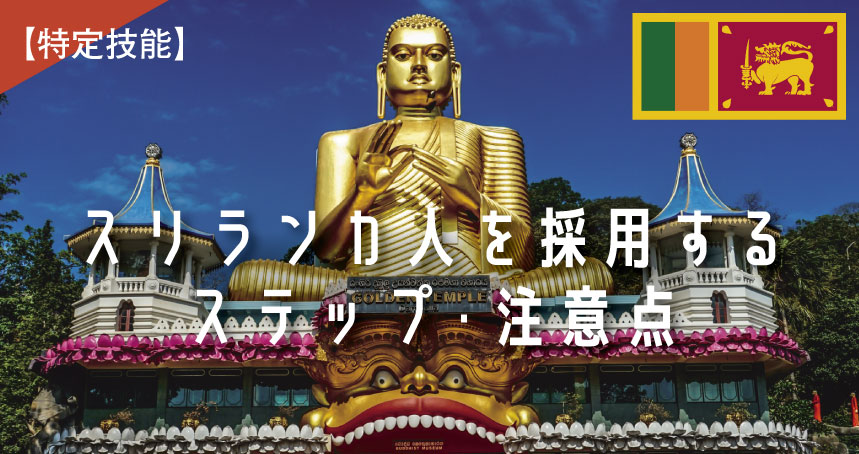
2024/07/31
【特定技能】スリランカ人を採用するステップ・注意点を解説。
-

2024/07/31
【特定技能】ネパール人を採用するステップ・注意点を解説。


